介護施設のレクリエーション担当者の皆さん、日々のお仕事お疲れ様です。
レクリエーションの時間をいかに楽しく、そして効果的にできるか、日々お題探しに悩んでいませんか?
今回は、準備する道具もほとんどなく、誰でも簡単に参加できて、なおかつ大きな盛り上がりが期待できる「ジェスチャーゲーム」をご紹介します。
ジェスチャーゲームは、言葉を使わずに身振り手振りだけでお題を伝える遊びです。
この単純な遊びが、実は高齢者の心身に多くの良い効果をもたらします。
今回の記事では、
- ジェスチャーゲームを成功させるためのコツ
- 難易度別の豊富なアイデア一覧
- 人手不足の現場でも活用できるヒント
まで、幅広く解説します。
ぜひ、この記事を参考に、皆さんの介護施設でジェスチャーゲームをレクリエーションに取り入れてみてください。
きっと、参加者の生き生きとした笑顔が見られるでしょう。
ジェスチャーゲームの魅力と効果
ジェスチャーゲームは、ただのお遊びではありません。
高齢者の健康に多くのメリットをもたらす、非常に優れたレクリエーションです。

ジェスチャーゲームの効果
ジェスチャーゲームは、楽しむだけでなく、参加者の心と体に良い影響を与えます。
脳の活性化に繋がる
ジェスチャーゲームは、お題を考える側も、それを当てる側も、頭をフルに使います。
表現する方は、どうすれば伝わるかを考え、当てる方は、相手の動きを見て何を伝えたいのかを考えます。
このプロセスは、脳に良い刺激を与え、脳トレに非常に効果的です。
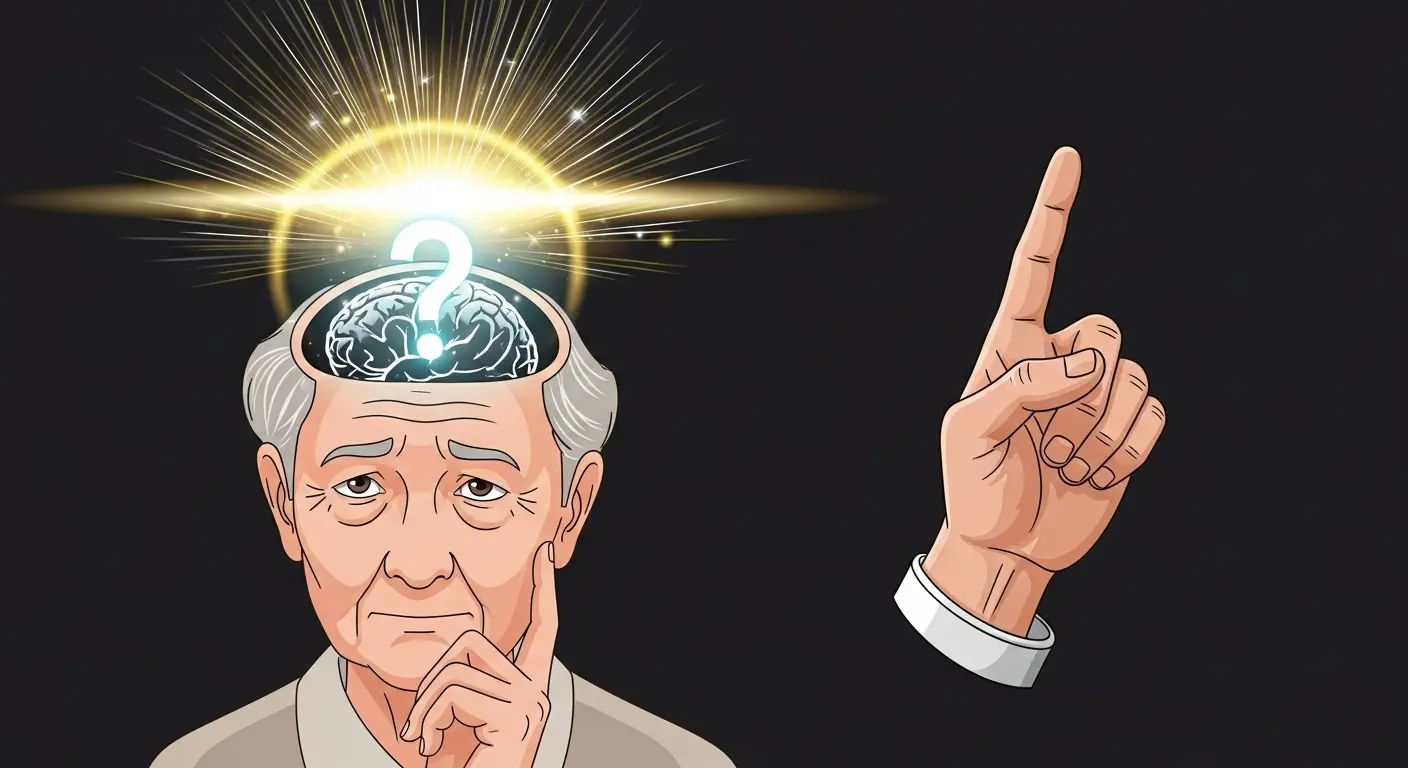
コミュニケーションを促す
言葉を使わないからこそ、身振りや手振り、表情から相手の気持ちを読み取ろうとします。
うまく伝わったときの喜びや、伝わらないときの笑いが、参加者同士の会話を自然と増やします。
コミュニケーションの活性化に繋がります。
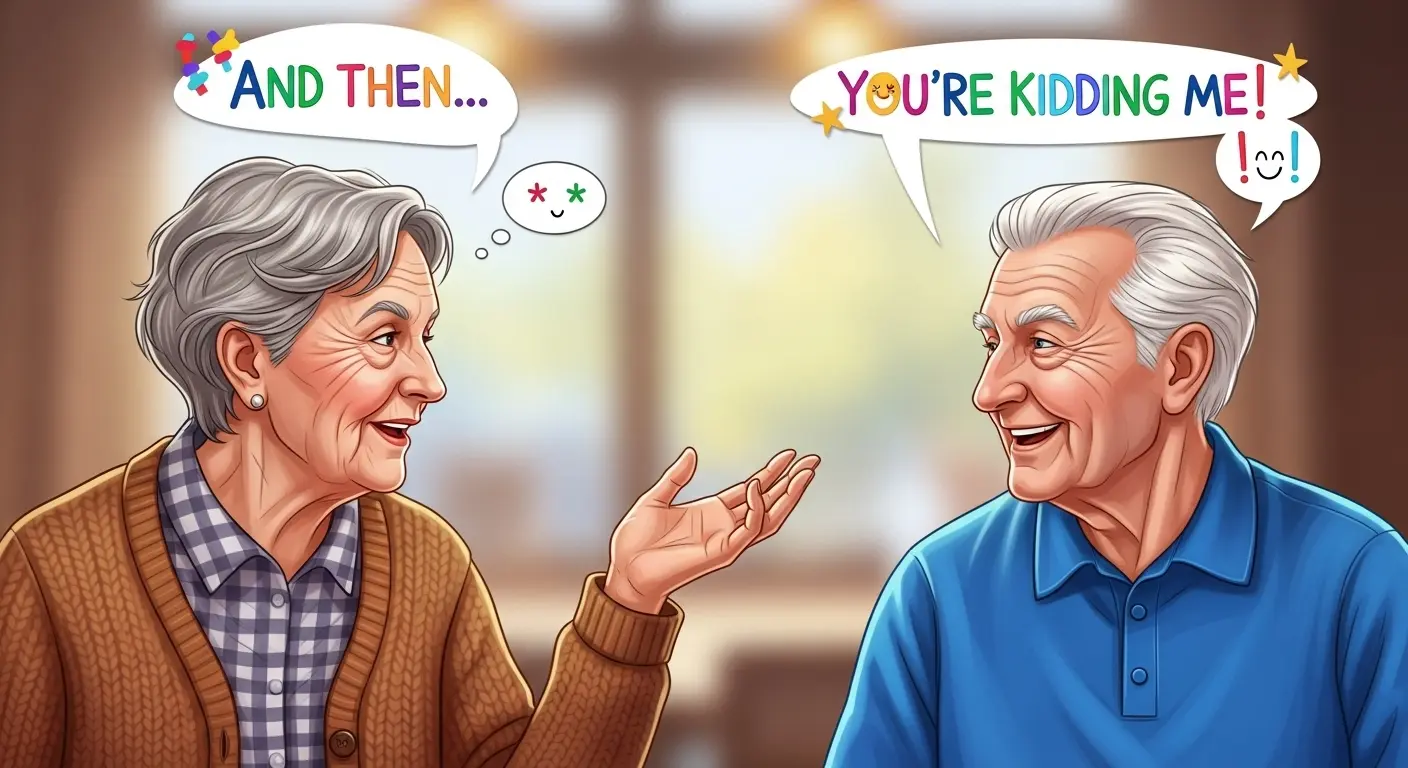
身体機能の維持と向上
ジェスチャーゲームでは、
- 立つ
- 座る
- 腕を伸ばす
- 指を動かす
など、様々な動作を行います。
これらの動きは、無理なく体の機能を使えるため、
- 日常的な運動不足の解消
- 機能訓練の一環
としても活用できます。
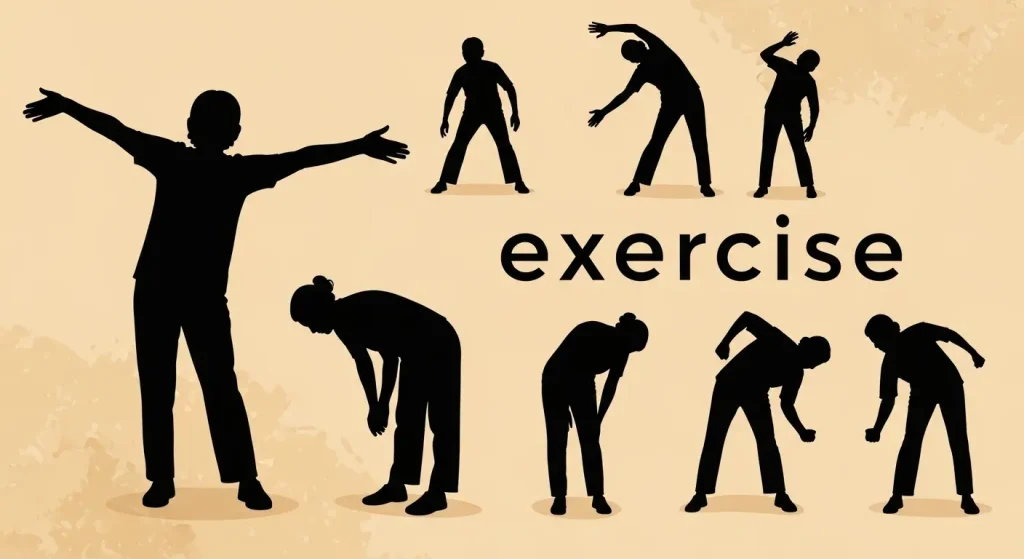
ジェスチャーゲームのお題一覧
ジェスチャーゲームを盛り上げるためには、お題選びが重要です。
ここでは、高齢者の方がイメージしやすく、楽しく取り組めるお題を難易度別に紹介します。
また、お題をどう表現するのか、具体的なヒントやコツも合わせて解説します。

超簡単なお題(初心者向け)
この難易度は、
- 初めてジェスチャーゲームを行う場合
- レクリエーションに慣れていない方
向けです。
- 認知機能が低下している方
- 身体を大きく動かすのが難しい方
こんな方でも、気軽に参加して楽しめることがポイントです。
なぜ簡単?
- 日常的に見慣れている
- あるいは習慣として身についている
単純な動作や、誰でも知っている身近な動物がテーマになっているからです。
特別な道具は必要なく、表現方法もシンプルで分かりやすいので、正解を出すことよりも、体を動かす楽しさや、みんなで笑い合うことに重点を置くことができます。
スタッフは、まずお手本を見せて、全員で一緒にやってみることをおすすめします。
- 動作系:
- 歩く: 足踏みをしたり、腕を大きく振る。
- 走る: その場で駆け足をする、腕を勢いよく振る。
- 食べる: お箸やスプーンを持っているような手の動きで口に運ぶ。
- 眠る: 手を顔に当て、目を閉じる。
- 電話をかける: 受話器を持つような手で耳に当て、口を動かす。
- 歯磨き: 歯ブラシを持つ手で歯を磨く動作。
- 顔を洗う: 両手で水をすくう動作や、顔をこする動作。
- 掃除: ほうきを持っているような手つきで床を掃く。
- 洗濯: 洗濯物を干す、たたむ動作。
- 料理: 包丁で何かを切る、鍋をかき混ぜる動作。
- 動物系:
- 猫: 両手で猫のひげを作り、体を丸める。
- 犬: 四つん這いになって、舌を出す、尻尾を振る。
- ゴリラ: 胸を両手でたたく動作。
- ライオン: 顔の周りに手を広げ、大きな口を開けて吠える。
- 鳥: 両腕を広げて羽ばたく、片足で立つ。
- 魚: 手を合わせて左右に振る、口をパクパクさせる。
- カエル: しゃがんだり、両手でカエルの口を表現する。
- ゾウ: 腕を鼻に見立てて、垂らす。
- ペンギン: 両腕を広げず、体を左右に揺らす。
- ひよこ: 両手で小さなくちばしを作り、体を揺らす。

ちょっと難しいお題(中級者向け)
この難易度は、ジェスチャーゲームの基本に慣れてきた方におすすめです。
単一の動作だけではありません。
- 複数の動きを組み合わせる
- 少し前の時代に流行したこと
- 特定の職業
など、参加者の経験に依存するテーマが含まれます。
なぜちょっと難しい?
単純な動きだけでは伝わりません。
- より細かい動作
- ストーリー性を持たせた表現
が必要になります。
しかし、この「考える」プロセスが脳への良い刺激となります。
脳トレとしての効果が期待できます。
チーム対抗戦にすると、お互いにヒントを出し合うなど、より活発なコミュニケーションが生まれるでしょう。
- 日常系:
- 買い物: カートを押す、お財布からお金を出す。
- 食事の準備: 材料を洗う、お皿に盛り付ける。
- 花に水をあげる: ジョウロを持つ手の形、水が落ちる様子を表現。
- 電車に乗る: 吊り革につかまる、揺れている様子を表現する。
- ゴルフ: クラブを振る動作、ボールを追いかける様子。
- 釣り: 釣り竿を投げる動作、リールを巻く動作。
- ラジオ体操: 腕を大きく回す、体を曲げる動作。
- カラオケ: マイクを持ち、歌っているように口を動かす。
- 野球を観る: グローブを持つ動作、バッターの構え。
- 水泳: クロールや平泳ぎの動作。
- 職業系:
- 警察官: 敬礼をする、笛を吹く。
- 消防士: 消防ホースを引く動作、はしごを登る動作。
- 医者: 聴診器を当てる、注射を打つ。
- 先生: 黒板に書く動作、指をさす。
- 歌手: マイクを持って歌う、スポットライトを浴びる。
- 駅員さん: 電車のドアが閉まる合図をする。
- 大工さん: ハンマーを打つ、ノコギリを引く。
- お寿司屋さん: 寿司を握る動作、大将のポーズ。
- 野球選手: バットを構える、ボールを投げる。
- 花屋さん: 花のにおいをかぐ、花束を作る。

さらに難しいお題(上級者向け)
表現力や発想力に自信のある方向けの、より複雑で面白いお題です。
参加者同士が協力して答えを探す楽しさが、大きな盛り上がりを生み出します。
なぜさらに難しい?
- 抽象的な概念
- 複数の登場人物
- 複雑なシーン
を表現する必要があるからです。
例えば、
- 歌や映画のタイトル
- 季節のイベント
など、具体的な動作に加えて、その背景にあるイメージを伝える力が必要です。
しかし、その分、答えが分かった時の喜びはひとしおです。
- スポーツ系:
- テニス: ラケットを振る動作、ボールを拾う。
- サッカー: ボールを蹴る、ゴールキーパーのポーズ。
- バスケットボール: ボールをドリブルする、シュートを投げる。
- バレーボール: スパイクを打つ、レシーブをする。
- スキー: ストックを持つ、滑降するポーズ。
- ボーリング: ボールを投げるフォーム、ピンが倒れる様子。
- 卓球: ラケットを持つ、小さなボールを追いかける。
- 縄跳び: 縄を回す動作、ジャンプする。
- スケート: 手を広げ、滑るように動く。
- マラソン: 疲れた様子で走る、水を飲む動作。
- 季節のイベント系:
- お花見: 桜の木を見上げる、お弁当を広げる。
- 七夕: 願い事を書く、笹を飾る。
- 運動会: 玉入れ、パン食い競争の動作。
- クリスマス: サンタクロースがプレゼントを運ぶ。
- お正月: お餅をつく、羽子板をする。
- 節分: 鬼のお面をかぶり、豆をまく。
- お祭り: 太鼓をたたく、うちわで扇ぐ。
- 紅葉狩り: 葉っぱを拾う、落ち葉を踏む。
- 雪だるま作り: 雪を丸める、雪を積む。
- 潮干狩り: 熊手で砂をかく、アサリを見つけて喜ぶ。

ジェスチャーゲームの成功ポイント
ジェスチャーゲームをただのお題当てクイズで終わらせないための、成功のポイントをご紹介します。

盛り上がる工夫とルール作り
参加者全員が楽しめるようなルールや工夫をすることで、ゲームはより一層面白くなります。
チームを組んで協力させる
チーム対抗戦にすることで、競争心が生まれ、チーム内で協力し合う姿が見られます。
お題を当てる側も、みんなで答えを考えることで、一体感が生まれます。
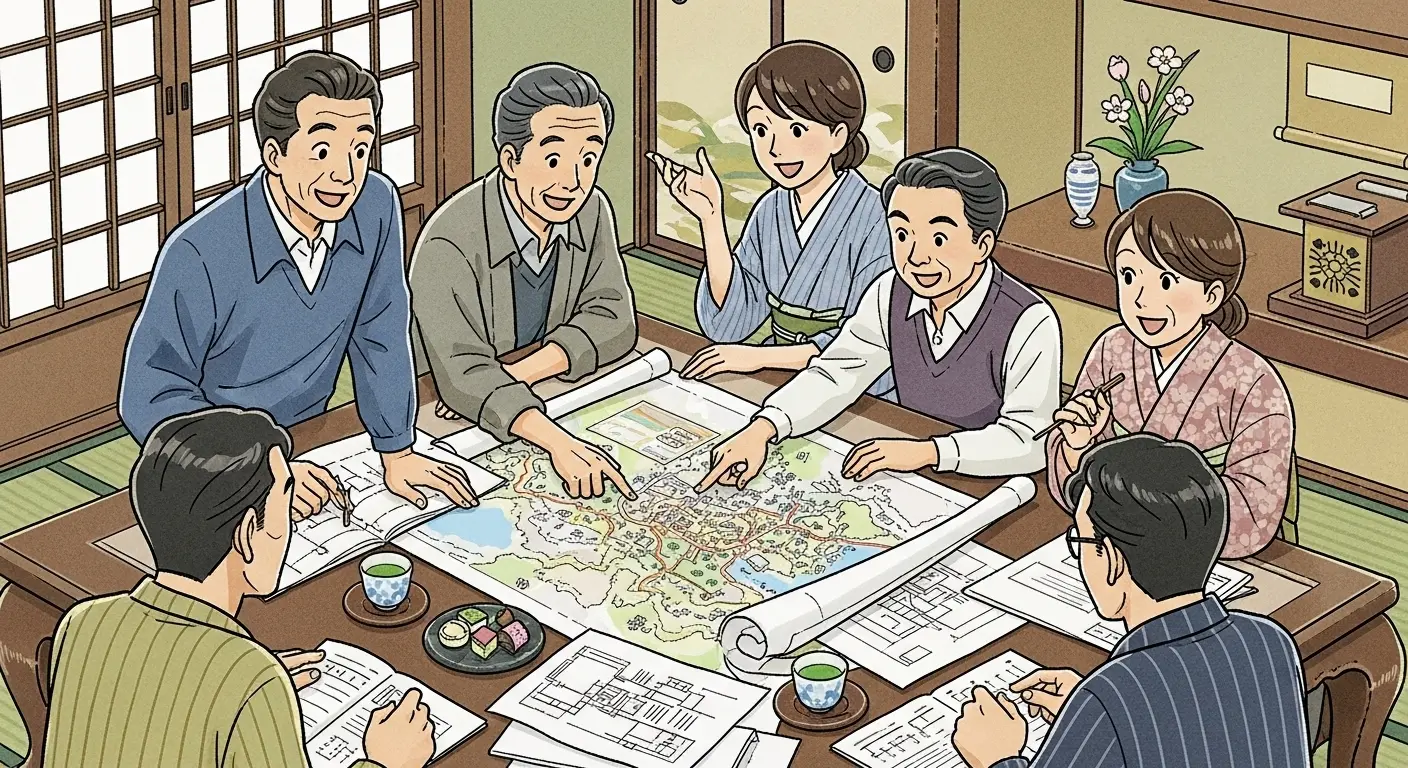
ヒントを出すルールを設ける
「ヒントは一言だけ」「ヒントは音だけ」など、ヒントの出し方を工夫することで、ゲームの難易度を調整できます。
これにより、答えがわからなくても諦めずに楽しめるでしょう。

参加者に合ったお題を選ぶ
- 参加者の個性や趣味
- 昔の経験
などを考慮してお題を選ぶと、より感情移入しやすくなります。
表現も豊かになります。
例えば、
- 野球好きの方には「野球のピッチャー」
- 料理好きの方には「料理」
といったお題を準備すると良いでしょう。
介護現場ならではの注意点
安全に、そして誰もが安心して楽しめるよう、いくつか注意すべき点があります。

安全第一で実施する
椅子に座って行うなど、転倒の心配がないよう、安全を確保した上で行いましょう。
無理な動きをさせることなく、できる範囲のジェスチャーを促すことが大切です。

個別の状態に合わせた配慮
認知症の方は、ルールを理解するのが難しい場合があります。
その場合は、ルールをより単純にしたり、職員が一緒にジェスチャーをしたりしてサポートしましょう。
人手不足の介護現場でもジェスチャーゲームを成功させるヒント
山口県の多くの介護施設が抱える人手不足の悩み。
そんな状況でも、ジェスチャーゲームは工夫次第で効果的に活用できます。

介護施設の職員向けサービスを活用
弊社では、山口県内の介護施設向けに、施設紹介の動画制作や施設内で360度動画を通じて、足踏みや体操などを行う映像系サービスを提供しています。
これらのサービスを活用することで、レクリエーションの幅が広がり、スタッフの負担軽減にもつながります。
360度動画制作ガイド:ビジネスに活かすためのステップバイステップ解説
よくある質問
Q1. ジェスチャーゲームのルールがうまく伝わりません。どうすればいいですか?
ルールが難しい場合は、最初は職員がお題のジェスチャーをやってみせて、「これは何でしょう?」と問いかけるところから始めましょう。
簡単な動作の例をいくつか見せることで、参加者も徐々にルールを理解していきます。
Q2. 認知症の方でも楽しめますか?
はい、楽しめます。認知症の方には、昔の経験に基づいたお題(例:洗濯、料理など)や、身近な動物(例:猫、犬)など、馴染みのあるお題を選ぶと良いでしょう。
言葉が出なくても、身振り手振りで表現できることが、大きな自信につながります。
まとめ
ジェスチャーゲームは、高齢者の心身の健康を促進します。
コミュニケーションを活発にする素晴らしいレクリエーションです。
お題の選び方やルールの工夫次第で、誰もが笑顔で参加できる楽しい時間となります。
この記事でご紹介したアイデアやポイントを参考に、ぜひ皆さんの介護施設でジェスチャーゲームを取り入れてみてください。
そして、参加者一人ひとりの個性と笑顔を引き出すきっかけとなることを願っています。



コメント